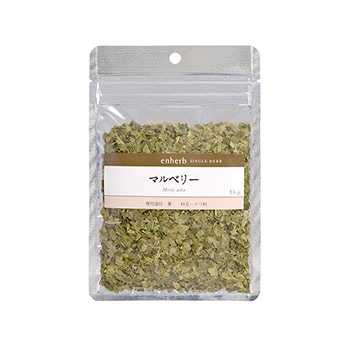街路樹には新緑が生い茂り、あぜ道には色とりどりの花が咲いています。
街路樹には新緑が生い茂り、あぜ道には色とりどりの花が咲いています。中でも、最も身近な野草として親しまれているタンポポは、寒い冬を越すために地中深くまで根を張り養分を蓄えています。
そんな生命力、繁殖力に優れたタンポポは「ダンディライオン」と呼ばれ、古くから根も葉もハーブとして利用されてきました。
そこで今回は、厳しい冬を乗り越え春を待つ、大地と太陽のチカラをしっかりと蓄えた「ダンディライオン」をご紹介します。
由来はライオンの歯?
 日本でもお馴染みの野草であるセイヨウタンポポ。
日本でもお馴染みの野草であるセイヨウタンポポ。ダンディライオンの名はその葉の形状から、フランス語で「ライオンの歯」を意味する「dent de lion」に由来します。
 セイヨウタンポポは明治時代に日本に帰化した種で、在来種のカントウタンポポが春にのみ花をつけるのに対し、こちらは一年を通して全国各地で花が見られます。
セイヨウタンポポは明治時代に日本に帰化した種で、在来種のカントウタンポポが春にのみ花をつけるのに対し、こちらは一年を通して全国各地で花が見られます。
排出をサポートしたい時に◎
 古くから、花を含む全草がサラダなど食用にされてきました。
古くから、花を含む全草がサラダなど食用にされてきました。フランスでは、葉が野菜として「おねしょ草」を意味する「Pissenlit(ピサンリ)」の名で市場に並びます。
ヨーロッパで薬草として用いられるようになったのは15世紀頃といわれ、漢方でも「蒲公英(ぼこうえい)」の生薬名で根が使われるなど、世界中で役立てられてきた薬草のひとつ。
カラダに溜まった不要なモノを排出するチカラがあり、特に根に含まれる苦味成分が消化を助けるため、消化不良のときにも役立ちます。
カラダの中をすっきりきれいに!
 ハーブティーでは、根(ルート)と葉(リーフ)を用います。
ハーブティーでは、根(ルート)と葉(リーフ)を用います。外用で使われることもあり、根・葉ともにクレンジングのイメージのハーブです。
 地中深く真っ直ぐに伸びる根は、苦みが最も強くなる6月頃に収穫するのがよいとされ、煎った根のティーはとても香ばしく、お子さまや妊娠中の方にもお楽しみいただけるカフェインレスの〈タンポポコーヒー〉として親しまれています。
地中深く真っ直ぐに伸びる根は、苦みが最も強くなる6月頃に収穫するのがよいとされ、煎った根のティーはとても香ばしく、お子さまや妊娠中の方にもお楽しみいただけるカフェインレスの〈タンポポコーヒー〉として親しまれています。大地と太陽の力を蓄えたダンディライオンは、ココロの奥まで軽くクリアにし、活動的な日々を力強くサポートしてくれるでしょう。

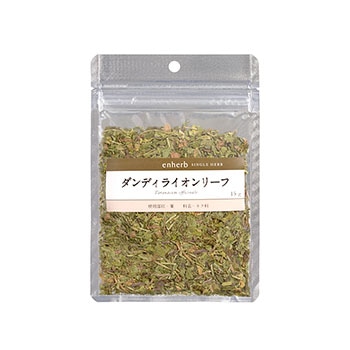





 4月23日(水)より商品名も新たになった季節限定ハーブティー「気分爽快! 晴れやか前線 ライムレモングラス茶」。
4月23日(水)より商品名も新たになった季節限定ハーブティー「気分爽快! 晴れやか前線 ライムレモングラス茶」。 【材料/4人分】
【材料/4人分】 寒天は海藻が原料の健康食品。
寒天は海藻が原料の健康食品。![[限定]気分爽快!晴れやか前線 ライムレモングラス茶(茶葉 / 50g(約12杯分))](/img/simpleblog/180/goods/4412233-11_dbab279bb11541d1a61fed7d53a77147.jpg)




 お正月気分も抜け、忙しい日常が戻ってきました。
お正月気分も抜け、忙しい日常が戻ってきました。 セイヨウタンポポの葉。フランスでは、「おねしょ草」を意味する「Pissenlit(ピサンリ)」の名で市場に並びます。
セイヨウタンポポの葉。フランスでは、「おねしょ草」を意味する「Pissenlit(ピサンリ)」の名で市場に並びます。 根菜として親しまれている“ごぼう”のこと。欧米ではおもに健康サポートハーブとして活用されてきました。
根菜として親しまれている“ごぼう”のこと。欧米ではおもに健康サポートハーブとして活用されてきました。 紫色の花を咲かせるアザミの一種で、使用部位は小さな種子。
紫色の花を咲かせるアザミの一種で、使用部位は小さな種子。 ハーブティーに使われるのは種子。インドでは、食後にローストされたフェンネルシードがよく出されますが、これは消化をサポートする働きがあるため。
ハーブティーに使われるのは種子。インドでは、食後にローストされたフェンネルシードがよく出されますが、これは消化をサポートする働きがあるため。 糖質や脂質を控え、サラダやスープなど野菜中心の食事にしてみてください。
糖質や脂質を控え、サラダやスープなど野菜中心の食事にしてみてください。 和食中心のお弁当は、脂質の摂りすぎや食べすぎを防ぐことができます。
和食中心のお弁当は、脂質の摂りすぎや食べすぎを防ぐことができます。 酸素をたくさん取り入れる有酸素運動で、ココロもカラダもすっきり!
酸素をたくさん取り入れる有酸素運動で、ココロもカラダもすっきり!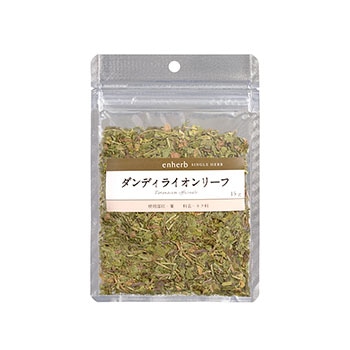





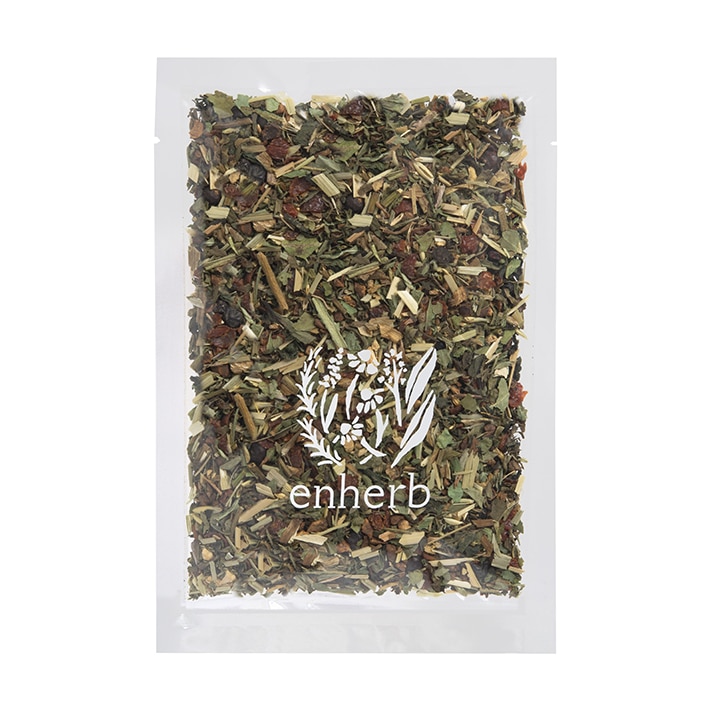
 秋が深まり、少しずつ冬の気配が感じられるようになってきました。
秋が深まり、少しずつ冬の気配が感じられるようになってきました。 コショウ、クローブとならび、旧約聖書にも登場する世界最古のスパイスのひとつ。
コショウ、クローブとならび、旧約聖書にも登場する世界最古のスパイスのひとつ。 シナモンは、クスノキ科に属する常緑樹の樹皮。
シナモンは、クスノキ科に属する常緑樹の樹皮。 風味付けに利用されることの多いシナモンですが、その働きかけも◎
風味付けに利用されることの多いシナモンですが、その働きかけも◎![[限定]黒豆シナモンしょうが茶(ティーバッグ / 30包)](/img/simpleblog/42/goods/4412334-11_3225445d04904b6f9d9481a15ff8760e.jpg)

 梅雨が明けると、本格的な夏がやってきます。
梅雨が明けると、本格的な夏がやってきます。 夏のカラダづくりには、きちんと汗をかけるカラダにするため、体内の熱をスムーズに放出できるチカラをつけることが大切です。
夏のカラダづくりには、きちんと汗をかけるカラダにするため、体内の熱をスムーズに放出できるチカラをつけることが大切です。 そんな時に助けになるのは、コーヒーや紅茶と共に、世界三大飲料のひとつである「マテ」。
そんな時に助けになるのは、コーヒーや紅茶と共に、世界三大飲料のひとつである「マテ」。 アロマテラピーでも「ハニーマートル」や「レモンティートゥリー」など、気持ちをシャキッとさせ、心身を活性させてくれる精油がおすすめ。
アロマテラピーでも「ハニーマートル」や「レモンティートゥリー」など、気持ちをシャキッとさせ、心身を活性させてくれる精油がおすすめ。



 食欲不振になりがちな夏。
食欲不振になりがちな夏。 地中海沿岸原産のセリ科の多年草。
地中海沿岸原産のセリ科の多年草。 ハーブティーでは、芳香に富んだ果実を用います。
ハーブティーでは、芳香に富んだ果実を用います。 古代ギリシャ語では、フェンネルを「Marathon(マラトン)」といいますが、これは「細くなる」を意味する「maraino(マライノ)」に由来します。
古代ギリシャ語では、フェンネルを「Marathon(マラトン)」といいますが、これは「細くなる」を意味する「maraino(マライノ)」に由来します。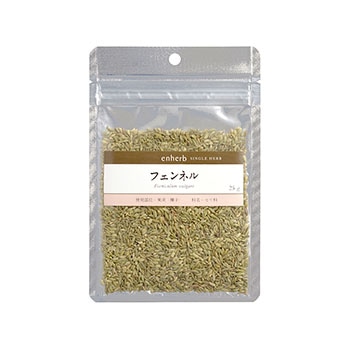





 暑からず寒からず、カラッと過ごしやすい秋晴れが続いています。
暑からず寒からず、カラッと過ごしやすい秋晴れが続いています。 マルベリーは、葉が蚕(カイコ)の飼料である桑(クワ)のこと。
マルベリーは、葉が蚕(カイコ)の飼料である桑(クワ)のこと。 桑の歴史は古く、日本には、2~3世紀頃、蚕とともに中国より伝来したと言われています。
桑の歴史は古く、日本には、2~3世紀頃、蚕とともに中国より伝来したと言われています。 葉には、カルシウムや鉄分、食物繊維など、豊富な栄養素に加え、注目の成分「デオキシノジリマイシン」を含んでいます。
葉には、カルシウムや鉄分、食物繊維など、豊富な栄養素に加え、注目の成分「デオキシノジリマイシン」を含んでいます。